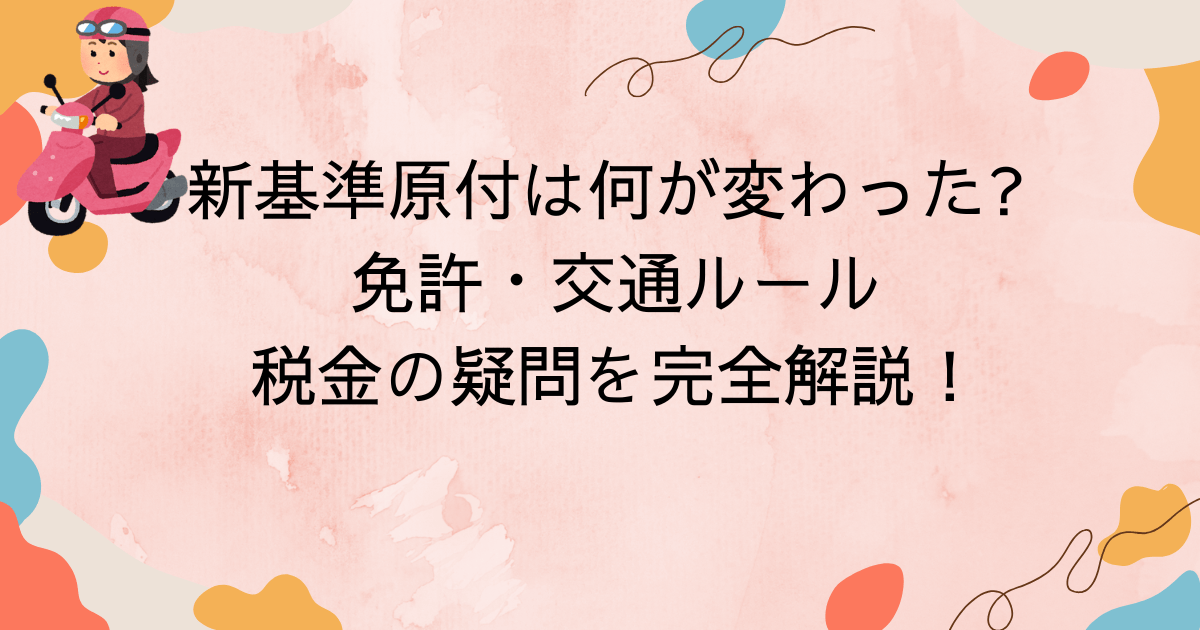2025年4月、原付バイクの世界に大きな変化が訪れ「新基準原付」という新しい区分が誕生しました。
これまでの常識が大きく変わろうとしています。
「125ccのバイクが原付免許で乗れるようになった」という話を聞いて、気になっている方も多いのではないでしょうか。
でも実は、この制度には意外な落とし穴があるんです。「125ccなら何でも乗れる」と思っていたら大間違いです。
知らずに乗ってしまうと、無免許運転になってしまう可能性もあります。
この記事では、新基準原付について「結局何が変わったの?」という疑問にお答えします。
この記事で分かること
- 免許
- 交通ルール
- 税金
以上の3つのポイントから分かりやすくお答えします。これから原付を買おうと思っている方も、すでに持っている方も、ぜひ最後まで読んでみてください。
新基準原付とは?免許で乗れる範囲が広がった

新基準原付とは、総排気量125cc以下で最高出力4.0kW(5.4馬力)以下に制御されたバイクのこと。2025年4月1日から、原付一種の新しい区分として追加されました。
原付免許で乗れるのは「出力制限された125cc」だけ
ここが一番の注意点です。
原付免許で運転できるのは、あくまで最高出力4.0kW以下に抑えられた特定の125ccバイクだけ。普通の125ccバイク(原付二種)を運転すると無免許運転になってしまいます。
現在、ホンダから「スーパーカブ110 Lite」「クロスカブ110 Lite」「スーパーカブ110 PRO Lite」「Dio 110 Lite」の4モデルが新基準原付として発売されています。
これらの車種には「Lite」という名前が付いているので、見分けやすくなっています。
なぜこんな制度ができたの?
背景にあるのは、2025年11月から適用される厳しい排出ガス規制です。
従来の50ccエンジンでは、この規制をクリアすることが技術的にもコスト的にも難しくなってしまいました。
50ccバイクは日本で約433万台も使われていて、生活の足として欠かせない存在です。
そこで国とメーカーが話し合い、排ガス規制に対応しやすい125ccクラスをベースに、出力を抑えることで原付として扱える新基準が生まれました。
新基準原付の交通ルールは従来と同じ
「125ccなのに30km/h制限?」と驚く方も多いでしょう。
新基準原付の交通ルールは、従来の50cc原付とまったく変わりません。
守るべき主な交通ルール
- 最高速度: 30km/h以下
- 右折方法: 二段階右折が原則
- 二人乗り: 禁止
- 高速道路: 走行不可
- ヘルメット: 着用必須
- 積載重量: 30kg以下
排気量が大きくなっても、法律上は「原付一種」として扱われるため、これらの制限はすべて継続されます。
出力を4.0kW以下に抑えることで、従来の原付と同等の安全性を保っているからです。
従来の50ccバイクはどうなる?
現在乗っている50ccバイクは、そのまま乗り続けることができます。
ただし、2025年11月以降は新車の生産が終了する予定なので、今後は新基準原付への移行が進んでいくことになります。
新基準原付の税金とナンバープレート
税金面でも嬉しいニュースがあります。新基準原付の軽自動車税は、従来の50cc原付と同じ年額2,000円です。
ナンバープレートは白色
新基準原付には、50cc原付と同じ白色のナンバープレートが交付されます。
一方、出力制限のない普通の125ccバイク(原付二種)は、従来通りピンク色や黄色のナンバーなので、外見で区別できるようになっています。
登録時の注意点
新基準原付を登録する際は、最高出力が4.0kW以下であることを証明する書類が必要になる場合があります。
具体的には以下のいずれかです:
- 型式認定番号が記載された販売証明書
- 国土交通省認定機関発行の「最高出力4.0kW以下確認済書」
- 最高出力確認結果表示シール
これは、外見だけでは従来の原付二種と区別がつきにくいためです。
まとめ
新基準原付制度により、2025年4月から原付免許で乗れるバイクの選択肢が広がりました。
ただし、すべての125ccバイクに乗れるわけではなく、最高出力4.0kW以下に制限された特定の車種のみが対象です。
交通ルールは従来の50cc原付とまったく同じで、30km/h制限や二段階右折などの規制は継続されます。
税金は年額2,000円、ナンバープレートは白色と、50cc原付と同じ扱いになります。
新基準原付は坂道での走行がスムーズになり、信号待ち後の加速が改善されるなど、日常の移動がより快適になります。
これから原付を購入する方は、自分の使い方に合わせて、新基準原付か小型二輪免許の取得かを検討してみてください。